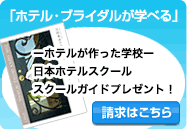得意技ですか?クレーム対応ですね

中島 宣由紀 氏
東京プリンスホテルパークタワー・東京プリンスホテル 副支配人
74年日本ホテルスクール卒業。
生粋のプリンスマンとして

日本ホテルスクールの前身はプリンスホテルスクールである。そのプリンスホテルスクールに1期生として入学した学生の中に中島さんがいた。ちなみに本連載の第一号に登場してもらったリッツ・カールトンの高野登日本支社長と中島さんは、同期で同じクラスだったそうだ。取材の数日前にも同窓会があったのだとか。
「当時は赤坂プリンスの敷地内に学校があったんですよ。学校といえども、校舎の床には赤じゅうたんが敷かれていまして、ホテルのような学校でしたよ。今から30年以上も前ですから、見学に行った私はかなり驚きました」
家が商売をやっていて接客というものを身近に見ていたから、将来は自分も接客の仕事をやるものだと自然に感じていた。そんな折、親戚からプリンスホテルが学校をつくるのだという話を聞いて興味を持った。
「よく兄に連れられてVANジャケットの展示会に行っていて、その展示会場が東京プリンスだったんです。帰りに満楼日園でジャージャー麺を食べさせてもらうのが楽しみでしてね(笑)。だからプリンスという名前にはなじみがあったんです」
学校の講師陣はほとんどがプリンスホテルから来ているホテルマンだったし、研修もプリンスホテルで行なった。中島さんは、そのままプリンスホテルに入社しているのだから、言ってみれば生え抜き中の生え抜きである。
「別にプリンスホテルスクールの卒業生だからといって、強制的にプリンスに入社したわけではありませんよ。高野のように海外に行ったのもいるし、クラスメートたちも御三家をはじめとしてさまざまな会社に巣立っていきました」
時代背景と同時に1期生という珍しさも手伝って、当時の学生は就職先に関しては引っ張りだこだったそうだ。一人に対して10社以上の会社がラブコールをしてきたというのだから、今の学生が聞いたらうらやましくて、よだれが出てしまう。御三家を筆頭に多くの選択肢があるなかで、中島さんはプリンスホテルを選んだ。完成されたホテルではなく、未来に向かってチャレンジしていくような会社に入りたかったからだ。
"チャレンジャー"
これは中島さんが自分の会社のスピリッツを言い表すときに使う言葉である。
クレームはチャンス
「得意技は何か」と聞かれたら、中島さんは「クレーム対応です」と答える。クレームは最大のチャンスだからだ。
「私は自分がホテルという世界に入って、心からよかったなあと思っているんです。お客さまに育ててもらって、ここまでくることができましたからね。長いホテルマン人生でクレームをたくさんいただきましたが、クレームを出してくれたお客さまたちの多くが今では私の顧客になっているんです」

まだ中島さんが20代で、レストラン「ポルト」でウエーターをやっていたころの話を聞いた。東京プリンスホテルの上顧客で、ある有名な作家がいた。この作家、いつも帽子をかぶっていて食事中もそれを脱ぐことがない。帽子はその作家にとって自他ともに認めるトレードマークなのであった。ホテルのレストランで帽子をかぶったまま食事をとることは、確かにマナー違反。30年前なら、その格好はなおさら目立つ。しかし、作家は意に介さぬ様子で帽子姿のまま食事をとっていた。
「これはおかしい」とだれもが思っていたはずだが、VIPに対してそれを指摘する勇気はない。マネジャーたちがしり込みしている最中に若手の中島さんが作家のテーブルに近づき、そして言った。「先生、お食事中は帽子をおとりになってください」
間違いは間違いであり、指摘することこそお客さまのためだと中島さんは固く信じていた。だからこそ言えたのだ。言い放った瞬間に上司が顔面蒼白になったのが目に浮かぶ。監督者にとって、若い信念とは時に脅威だ。
案の定、その作家先生は烈火のごとく怒りだし、中島さんの上司の謝罪も振り払ってレストランから出て行ってしまった。
「そのときは上司に叱られましたよ。『なんてことをしてくれたんだ』とね。でも、そのまま帽子をかぶったまま食事をしたんじゃ、先生が恥をかき続けると思ったものですから」
そんな事件の数日後、「ポルト」のスタッフが目を疑うような出来事が起きた。なんと作家先生が帽子を脱いで入店してきたのだ。
帽子を脱いで食事をしたその日から30年、作家先生は中島さんの顧客であり続けている。
「怒るというエネルギーを使うということは、相手がこちらに期待している証拠ではありませんか。怒るほうだって嫌な気分になるのです。最初から期待していなければ怒りもせずに帰って、そして二度と戻ってきてくれません。このホテルにまた来たいから怒ってくれるんです。その先生は新しくできたパークタワーにも頻繁にお越しくださいますよ。『ソフトはまだまだだな』と、いつもさまざまなご指摘をちょうだいしています(笑)」
クレームで一番大切なのは"何に対するクレームなのか"を絶対に見誤らないことだと、中島さんは教えてくれた。なかには解決策や代替案を提案できずに平身低頭して謝り続けるしかすべのないケースも多々ある。そんなときでも"この人は何に対してお怒りなのか"を見極めて、そこから目をそらさないことが大切。
「感覚的な表現をすれば、お客さまにはそれぞれの"温度"があるんです。その温度と同じ温度でこちらも対応しなければならない。クレームを言う側と言われる側に温度差があると、『おまえの態度は何だ!』と2次クレームが発生してしまいます。そうなっては収まるものも収まりません」
温度を察知することがサービス
中島さんの言う"温度"は何もクレーム対応のときのみに考えることではない。サービスの現場に立つならば常に相手の温度、その場の温度を察知する能力に長けていなければならないようだ。
「今日、ロビーに立っていまして、久保さんと近藤さんが入って来たとき、お顔は存じあげなかったのですが、すぐに分かりました。五感を働かせて人の温度を測れば分かることです」
確かに、われわれが東京プリンスホテルパークタワーのロビーに入ったとき、中島さんの視線はこちらを向いていた。熟練のホテルマンと待ち合わせをすると、そういうことが間々ある。レストランのレセプショニストたちのなかにも「お客さまが入店した瞬間に何を目的に来たかが分かる」とか、もっとすごいのになると「初来店の方でも、予約が入っていれば顔を見ただけで名前が分かる」というようなことを言う人がいる。
「それこそがホテルの価値ですよね。時計を見ながらレストランに入ってきたビジネスマンに、時間をかけた懇切丁寧なサービスをしていても何も喜ばれない。『早くお持ちできるのはカレーですよ』とか『コーヒーは先にお持ちしましょうか』という気配りが当たり前にできなければいけません。いつも相手の温度を察知しなくては」
そういった温度を察知してサービスすることを若い人に教育できているホテルが少ないと、中島さんは嘆く。
「"仏造って魂を入れず"の状態なんですよ。制服姿はとてもかっこいい。でも、魂が入っているのかどうか心配です。ホテルをハードで評価してもらう時代は終わりました。スタッフ一人ひとりの質がホテルの評価を決める時代です。"お客さまは神様"のスタンスではなく、お客さまに感動と興奮を与えられる感性あふれるエンターテイナーが必要です。小泉チルドレンではないですが、今後一流のプリンス・チルドレンをどれだけ育てられるかが、ホテルの評価を決定する最大のポイントだと私は思います」
テナントから形成されるブランド力

東京プリンスホテルと東京プリンスホテルパークタワーには、ホテル内セレクトショップとしてはかなり大規模な西武ピサが入っている。05年から中島さんはこちらの支配人も兼務する。
「東京プリンスの地下1階にある672坪のショップ、それとパークタワーの1階と地下にあるテナント10軒の管理運営を担当しています。いわゆるホテル業とは仕事の性質が違いますが、新しい発見があり楽しんでいます」
もちろんホテルの3本柱は宿泊・料飲・宴会だが、これからのホテルビジネスにおいてホテル内ショップのブランド力は大きな要素になるだろうと、中島さんは考えている。
「いかに良いテナントに入ってもらうかということも重要だと思います。エステなどは、そこを中心としてホテルのブランドが形成される可能性もありますから重要視しなければなりません。そして、ホテルに入ってもらったからにはテナントの皆さんもホテルのスタッフです。お客さまは区別しませんから、彼らにはホテルの精神を理解してもらうことが大事になります」
東京プリンスではテナントスタッフもホテル側と同じネームプレートを胸に着けている。中島さんは毎日のようにテナントを回り、彼らと話をする。生粋のプリンスマンとしてプリンスの精神を伝えるために。
(2006年取材)
中島 宣由紀 Nobuyuki Nakajima
74年専門学校日本ホテルスクール(旧プリンスホテルスクール)卒。同年㈱プリンスホテル入社。82年食堂部係長。90年長崎プリンスホテル開業準備室。91年レストラン改装準備室。92年北九州プリンスホテル開業準備室。93年企画部課長。97年営業推進部次長。98年食堂・宴会部次長。00年高輪・新高輪プリンスホテル食堂部次長。01年東京プリンスホテル食堂・宴会部長。02年東京プリンスホテル副支配人。05年東京プリンスホテルパークタワー・東京プリンスホテル副支配人(西武PISA・テナント担当兼西武PISA支配人)。